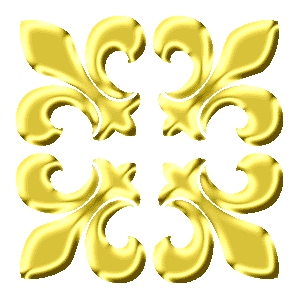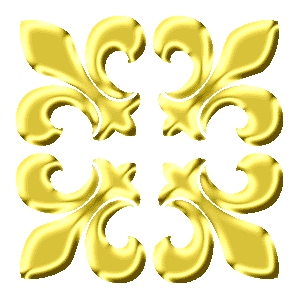| |
|
これら新旧2つの制度は別の制度だということに注意する必要があります。 |
| |
|
旧NISAでは、非課税期間終了前にロールオーバーすることで、次の非課税 |
| |
|
期間に移行することができました。 |
| |
|
しかし、2019年に投資をした分は、2023年末に非課税期間が終了してしまい |
| |
|
ます。(同様に2020年に投資をした分は、2024年に非課税期間が終了します。) |
| |
|
ロールオーバーはできず、そのまま放置すると、自動的に課税口座に移されて |
| |
|
しまいます。 |
| |
|
2019年投資分を、2023年末か2024年初の できるだけ価格が上昇したタイ |
| |
|
ミングでいったん売却して、非課税の売却益を受け取り、2024年に始まる新 |
| |
|
NISAの投資資金とする方法が、ひとつの戦略として検討に値します。 |
| |
|
なお、そのまま放置して課税口座に移行した場合には、非課税期間が終了 |
| |
|
する年末の移行時点の価格が、課税口座における取得価格になって、以降 |
| |
|
の売却益に 20.315% 課税されます。 |
| |
|
|
| |
|
引き続き、同じ先に投資をしたい場合には、買い直すことになりますが、年内 |
| |
|
であれば、課税口座になりますので、2024年早々に、新しいNISA枠(成長 |
| |
|
投資枠240万円 または つみたて投資枠120万円、あるいはその両方)を利用 |
| |
|
して非課税で投資をすることができます。 |
| |
|
|
| |
|
資金的に余裕のある人の場合には、毎年、成長投資枠240万円と つみたて |
| |
|
投資枠120万円の投資を5年間続けて、1,800万円の生涯枠を使い切るという |
| |
|
ことも可能です。 |